農学部・農場コレクション
コレクションの概要
農場博物館では、農場が田無(現 西東京市)に移転してからの時代、すなわち、1935(昭和10)年8月以降に、農場で実際に使われた農機具や、農学部・大学院農学生命科学研究科![]() で標本などとして収集された農機具・実験機器を、農学部・農場コレクションとしています。なお、駒場時代の農場で購入された後、引き続き田無の農場でも使われた農具を、農学部・農場コレクションとしている場合もあります
で標本などとして収集された農機具・実験機器を、農学部・農場コレクションとしています。なお、駒場時代の農場で購入された後、引き続き田無の農場でも使われた農具を、農学部・農場コレクションとしている場合もあります
よって、農学部・農場コレクションは、東京帝国大学農学部(1919(大正8)年改称)・東京大学農学部(1947(昭和22)年改称)・東京大学大学院農学生命科学研究科(1994(平成6)年改称、2000(平成12)年改組)の附属農場や研究室などで使用・収集されていた史料が主となっています
コレクションの紹介
- 画像をクリックすると拡大画像とタイトルがご覧になれます
- 拡大画像の上でのクリックやホイールで前後のコレクションがご覧になれます
- ブラウザ上部のボタンセットを使うとスライドショーなどでコレクションがご覧になれます
- 拡大画像タイトルにある
 をクリックすると解説がご覧になれます
をクリックすると解説がご覧になれます




































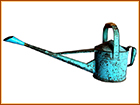














東大牛乳
「東大牛乳」瓶
![]() 画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます
画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます
日本で牛乳瓶が使われだしたのは、明治時代とされ、現在のような紙製のキャップになったのは、第2次世界大戦前後と推定されています。東大農場では、牛乳(加工乳)の販売開始当初は、市販の牛乳瓶を集めて使用していたようで、1965(昭和40)年頃から、オリジナルの「東大牛乳」瓶が使用されるようになったようです。画像(展示品)は、瓶詰「東大牛乳」の販売が終了した1975(昭和50)年に使用されていた180mL(1合)瓶で、古い瓶にはなかった「要冷蔵」の表示があります
東大農場では、1968(昭和43)年度から、乳が出る経産牛を約40頭、子牛の育成牛を約20頭という規模で、乳牛の飼育がなされていました。しかしながら、国家公務員の定員削減による教職員数の減少に加えて、学生実習の内容を充実させる目的で、1975(昭和50)年度末をもって、瓶詰の成分無調整「東大牛乳」の販売を終了しました
1971(昭和46)年度の「東大牛乳」生産量は946,116本、単価はこの年の6月に2円値上げして16円で、1975(昭和50)年度の生産量は640,555本で、単価は28円でした。「東大牛乳」は職員が個人宅へ直接配達するのではなく、谷戸住宅・日鉱アパート・第9住宅・第3住宅・第5住宅・ふみえ会・北原住宅・第14住宅・田無病院・東大原子核研究所住宅・東大多摩第二宿舎・東大田無学寮などの団地単位に納入されていました
「東大牛乳」の生産中止の後、豚・ニワトリ・めん羊が飼育されるようになり、家畜の種類は田無への移転のときのにぎわいを取り戻しましたが、これらの家畜の飼育も1979(昭和54)年度末までに終了し、1988(昭和63)年に乳牛の飼育も終え、乳牛に替わって飼育されていた肉牛の飼育も、2006(平成18)年に終了してしまいました

